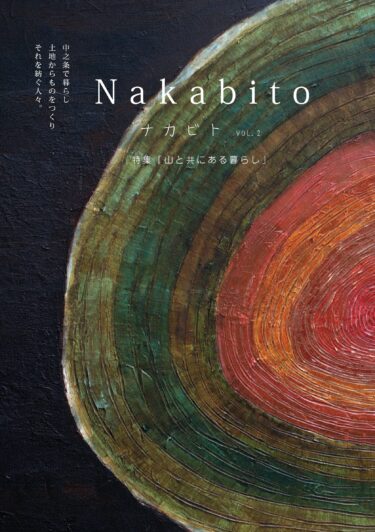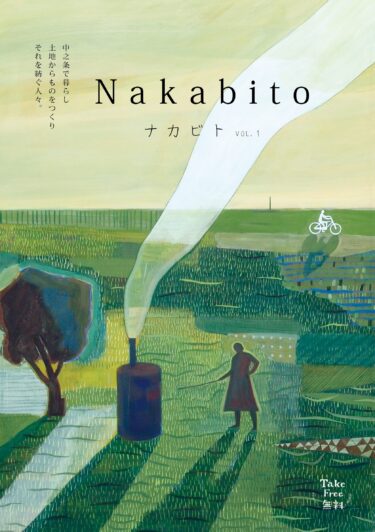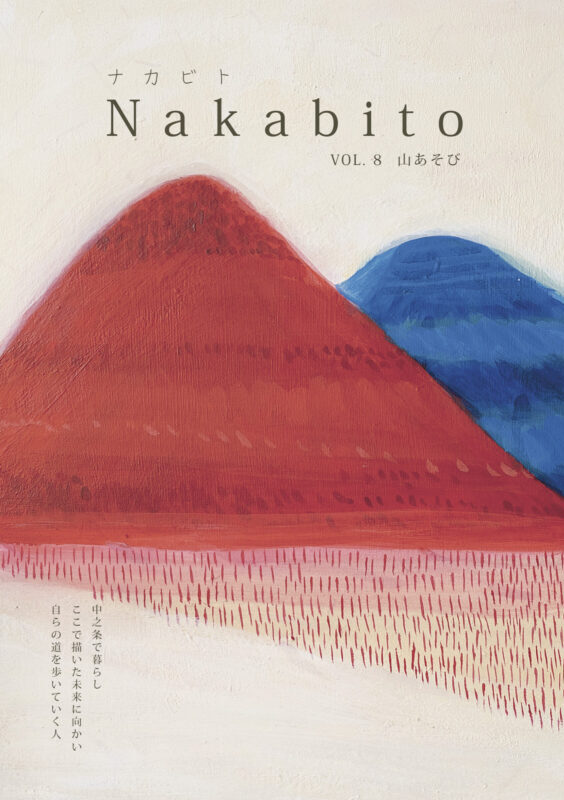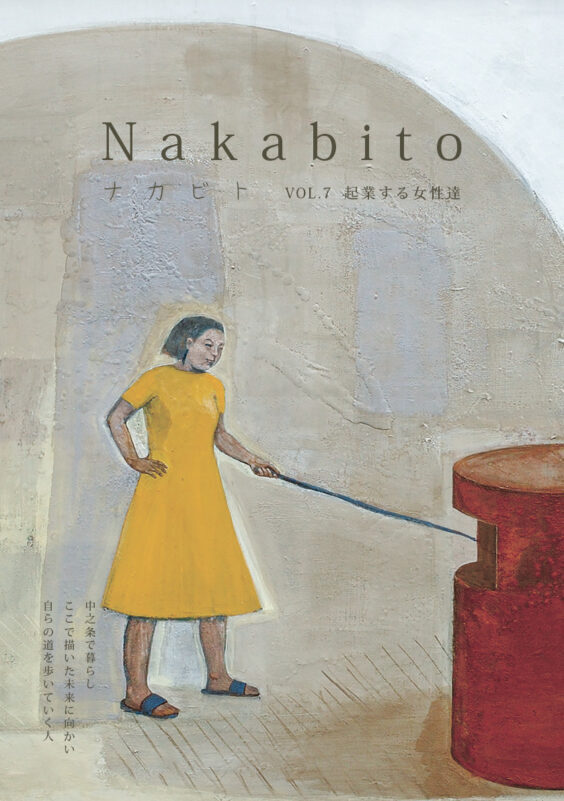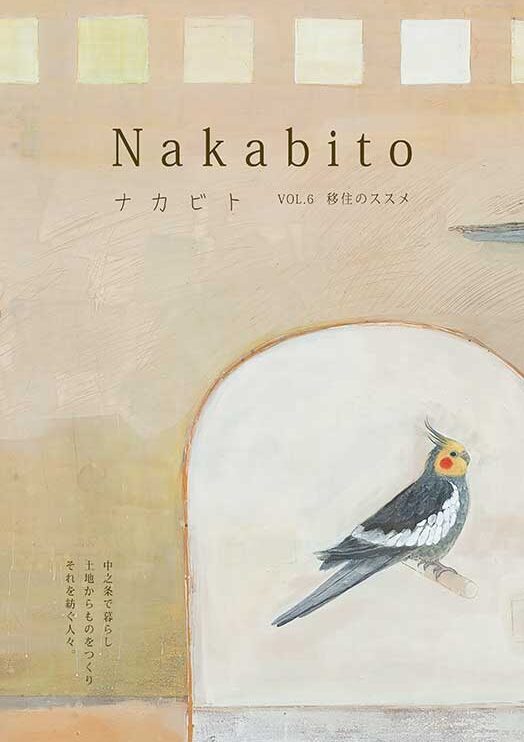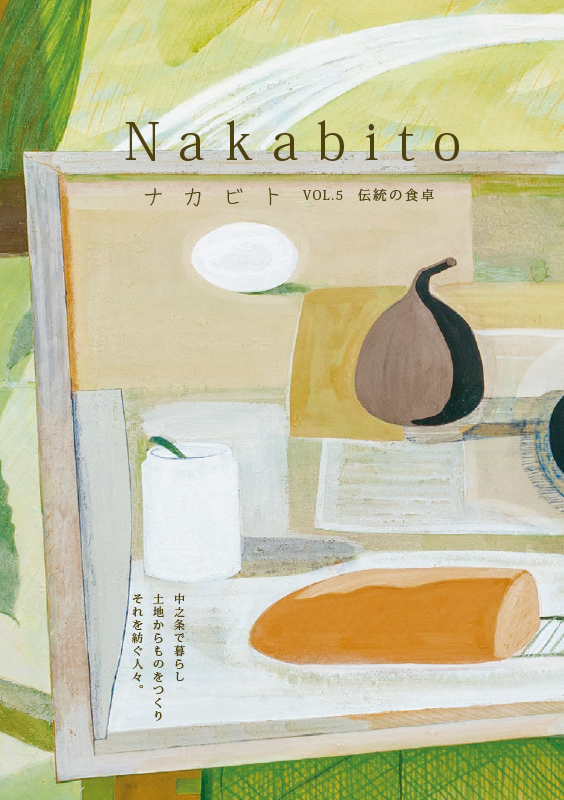古川さんは、「最後は概念になりたい」と言った。美術作家としてモノを作り続けてきた人が、形を持たない存在になりたい、というのは、とても印象的だった。
横浜から山深い六合(くに)のど真ん中にポッとやってきて、ときに悩みながらも鮮やかに、無邪気に、思いきり生き切っている。その充実感からの言葉なのか。それとも、生きるうえでのさまざまな苦悩からなのか、わからないけれど。その本当の意味は、本人にしか、わからない。
無心に制作に打ち込み、地元のお祭りではしゃぎ、壁を前に立ち止まっているときも。古川さんはいつも剥き出しで、ありのままをさらけ出している。そんな彼女だから、周りの人はどうしたって放っておけないのかもしれない。2017年中之条ビエンナーレ、六合の世立(よだて)での展示は、まさにその持ち味が生きた。地元の人がひとり、ふたりと制作に加わり、古川さんを中心にみんなで撚り上げた大作となった。それは本当に、古川さんでなければできない仕事だったのだと思う。
古川さんと六合との関わりは、2015年に遡る。その年の中之条ビエンナーレで、六合の赤岩という地区に約3ヶ月間滞在し、制作を行った。展示場所だった湯本家住宅の裏庭にテントを構え、大きな木の幹をゴロンと寝かせ、朝に夕に夢中で彫っていた、そのキラキラした眼差し、身体全体から生気を放つような古川さんの姿は、いまでも鮮明に思い出せる。
「〝コレコレ!〟って思ったんですよ。六合で体験するすべてが刺激的すぎて、自分の中に湧いてくるものがあった。生きることが楽しい!ってハッとした。汗水たらして体動かして、体いっぱいで笑って。地元の人に野菜をもらったら新鮮なうちに美味しく料理して、1日の終わりにほかの作家たちと食卓を囲む。次の日また制作に向かう。それだけで幸せ感じるんですよね、人って」
会期が終わった後、一度は出身地の横浜に戻った古川さんだけど、ほどなくして、ふたたび六合に舞い戻ってくることになる。その当時拠点にしていた横浜のアトリエから出なければならなくなったのだ。
「アトリエ中心に成り立っていた生活だったので、正直困ったなと思ったのですが、でもすぐに、だったらどこにでも行ける!これはチャンスだって思ったんです。どこにいる自分が一番好きかな? って考えたとき、すぐ『六合!』って。引っ越すなら仕事も必要、と調べてみたら、いまの仕事の募集を見つけたんです」
その仕事内容は、彼女いわく、「私しかいないでしょ、これできる人」というものだった。
それは、この地に昔から残る技、こね鉢やメンパ、こんこんぞうりやスゲムシロなどのスゲ細工といった伝統工芸や手仕事で町を活性化するという大役。「やるならば、ゼロから学びたい」と師匠たちに技を見せてもらい、技術を習得した。もともと木彫作家である古川さんは、木材や刃物の扱いを心得ており、素晴らしい技の担い手となった。道具の使い方も技術も、師匠たちのお墨付きだ。それがもう3年になる。必要な道具もひと揃えした。両端に柄のついたナタのような金物、センは、県内の刀職人に特注で作ってもらったもの。そのほかに必要な道具も、作れるものはすべて、六合の人たちの手を借りながら、六合の材料で作った。
「もともとちょっと山には苦手意識がありました。でも六合の人たちにとって、山は入っていく場所で、いろいろな恵みをいただくところ。山にへえって(入って)、猟したり山菜採ったり。木やツル、スゲなどの、身の回りの道具を作る材料も。そういう恵みを山から戴く、という感覚は、今までなかったなぁって」
古川さんのアトリエには、山のカケラがいっぱい。いろんな木の実がそれぞれに詰められた瓶が並び、木の枝の形をそのまま利用した小物かけが、なにげなく置いてある。かわいい形の種や、竹の皮から作られたアクセサリー。松ぼっくりをいくつも連ねてつくられた円形のオブジェ、乾燥させたスゲやワラの束はうずたかく積もり、壁に並んで掛かるゴワゴワの黒い帯は、くるみの木の皮だという。「木の皮を活かしたモノ作りが出来ないかなと思って。これを剥いでいてギックリ腰になったんですよ!」部屋の隅の照明に、繊細に張られた羽衣のようなクモの巣も「きれいだから」とそのままにしてある。一角にスゲムシロを敷いて、制作はそこでする。その脇には、木炭で描かれた力強い木の幹のドローイングがあった。
この部屋は、きっと古川さんの〝山〟なんだろうな。深い森の奥の、豊かな香りがするもの。
あらためて、古川さんにとって六合ってどんな存在?
「六合に来てめっちゃ変わったと思う。素の自分を解放された感じ。『出ていいよ!』って。古川葉子を広げてもらったと思います。人間としても作家としても。ただ単に六合が大好きってことだけじゃなくて、全部の感情がそこにある。ときには嫌になることだってある。でも傍にいてほしい。六合は家族のようなもの。『見てる? ちゃんと見てる?』って。六合に、私のことを見ていてほしい」