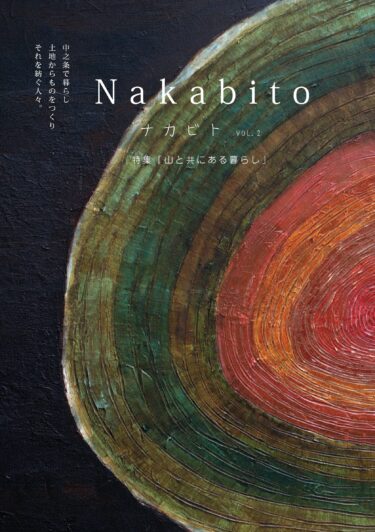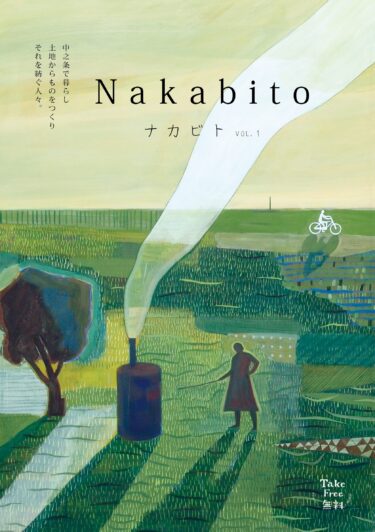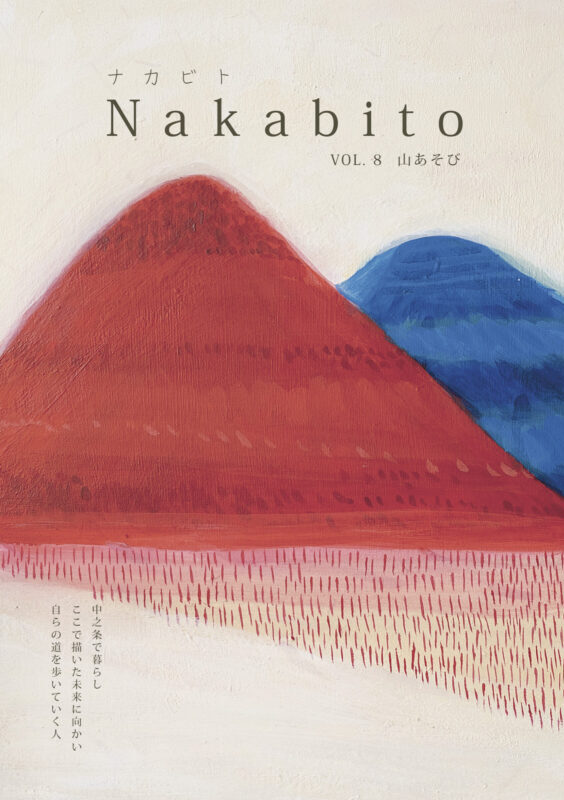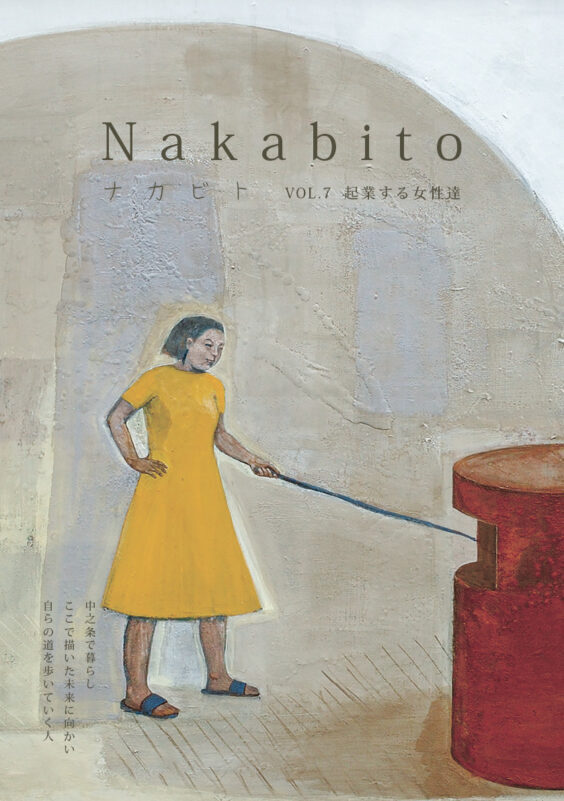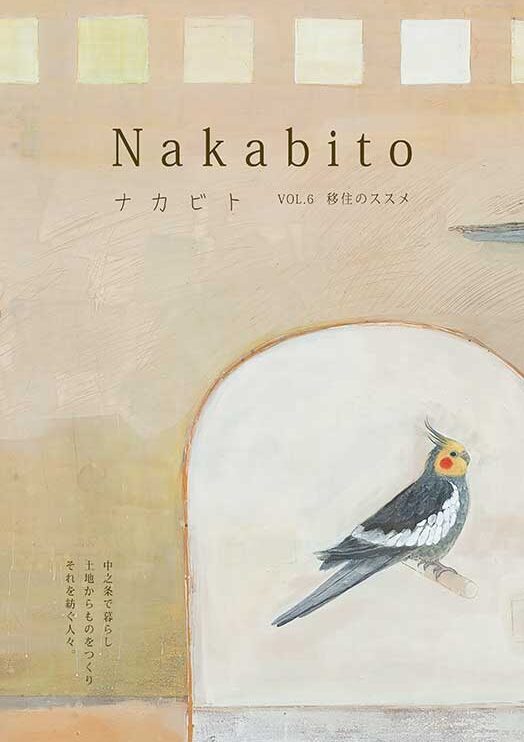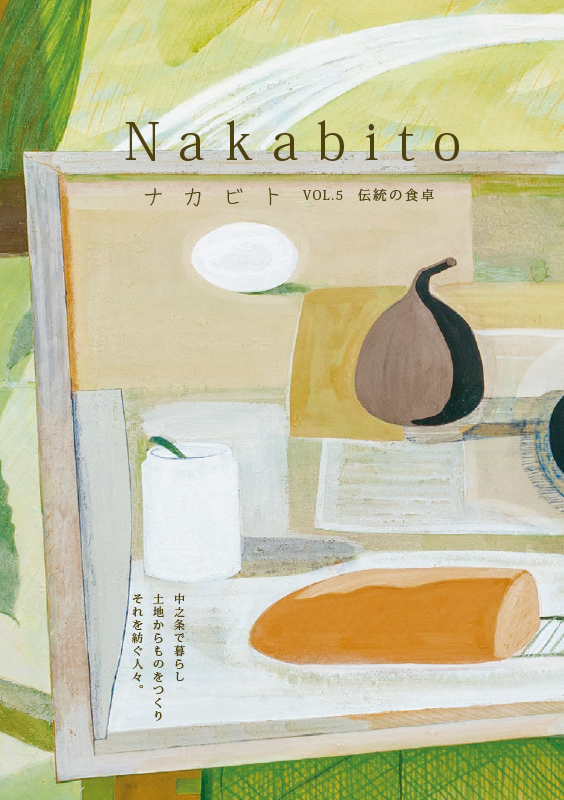─ 六合自慢のおっきなおっきな花豆。加工前の乾いたお豆はじいっとうずくまって、こちらの様子をうかがっている。手のひらいっぱいにすくい持つと、クスクスきゃっきゃとはにかむ子どもの笑い声が聞こえた気がした。いろいろな形、大きさ、きれいなピンク色と黒の個性的な模様、、、よく見ると色も微妙に違って黒の点々も豆それぞれ! なんともかわいく愛おしい。─
六合で作られる花豆は他の産地のものと比べ大粒です。高い標高と冷涼な気候が育みます。そのサイズだけで喜んでくれるお客さんもいるのだとか。
今にもムクムクと動き出して楽しいおしゃべりを始めそうな花豆たちを、甘く煮て缶詰にしているのは、六合の幸工房の本多さんご夫婦、康雄さんと康子さんです。目をかけ手間をかけ、愛情を込めて大切に作っています。
工房は秋色に色づき始めた山を背に建っていました。京塚温泉の入り口にある、かつて幼稚園だった建物。だからでしょうか。はしゃいで駆け回る子どもたちの温かい気配がほのかに残っています。一室をそのまま再利用した調理場は、とてもコンパクト。
今日は、素晴らしい晴天のぽかぽか陽気。お空に負けないほかほか笑顔で、本多さんご夫婦は迎えてくれました。
中に入るとさっそく調理場へ。巨大な圧力鍋や缶詰の機械の前で、康雄さんが作り方をおしえてくれました。
① まず、乾いた花豆を10時間水に浸してほとばす(群馬の方言で「(水に漬けて)ふやかす」)。
② 十分にほとびたらお豆を圧力鍋に移し、1時間ほど火にかけて煮え立ったらお湯をすべて捨てる。
③ もう一回新しい水を入れ30~40分かけて煮え立たせ、沸騰したら3~4時間とろ火で煮込む。
その後またお湯を捨て新しい水を入れ煮込む。この作業を何回も繰り返すことでお豆の灰汁を抜いていく。――これをしないと「口が曲がるほど苦い!」。愛らしい見た目に反して、意外にも剛情!
④ 灰汁を抜き終わってやっと味がつけられるようになる。
・・・お豆をおいしく柔らか~くするのには手間がかかるんですね。
味付けにもこだわりが。塩と砂糖。それだけ。保存料、甘味料などの添加物は一切なし。康雄さんいわく、昔のひとはこうしたシンプルな材料で本当においしく作ったのだそうです。
以前、帰省した息子の手土産に持たせた市販の花豆の甘煮が「甘すぎ」と不評。ならば、自分たちで作ってやろう!と。康雄さんの当時の意気込みが伝わってくるエピソードです。
食べてごらん、と缶詰を開けてくれました。一粒ほおばると、なるほど。大粒の花豆はふっくらやわらか。やさしい甘さはしつこくなく、いくつでも食べられそう!
できた花豆の甘煮は、康子さんの手によって缶にひとつひとつ丁寧に詰められていきます。康雄さんが煮て、康子さんが缶に詰めて、夫婦の連係プレーです。
たった二人だけの工場、懐かしさや温もりがいっぱい入った缶詰はこうして出来上がります。
「煮方はわたしが教えたんですよ。」康子さんが話してくれました。実は康雄さんの本職は植木屋さん。それまで豆を煮たことはありませんでした。中之条地区の出身の康子さんも花豆の煮方を知らなかったため、おばさんに教えてもらったそう。そんなふうに夫婦ふたり手探りで始まった花豆の甘煮づくり。はじめの1年は試作研究に明け暮れ、柔らかくなりすぎたり、固かったり、できてもうんまく(美味しく)なかったりと、幾度となく失敗も経験しました。そうして「だんだんと腕を上げていった」と康雄さん。現在の作り方にたどり着きました。
ご夫婦が花豆の缶詰づくりをすることになったきっかけは、集落の活性化のために特産品を開発しようという動きから。村おこしのために立ち上がった康雄さん・康子さんご夫婦の挑戦は2010年に始まり、今年で8年目。文字通り二人三脚で歩んできました。いまや昔ながらの素朴な味付けとふっくら大きな六合の花豆を求める声は全国各地からあります。「お得意さんもいるんですよ」康子さんは笑います。
写真を撮るために「もっとくっついて」と声をかけたら、「普段あんまりくっつかねぇから」なんて言いつつ恥ずかしそうに笑って並ぶ姿にこちらもほっこり。
「花豆以外にも作ってみたい缶詰がいくつかあるんだ」さらなる夢を語る康雄さん。
さあ、今年も二人の愛情を一身に受けて、お鍋の中でコトコト煮られる花豆たちのクスクス笑う声があの小さな工房から聞こえてきますよ。