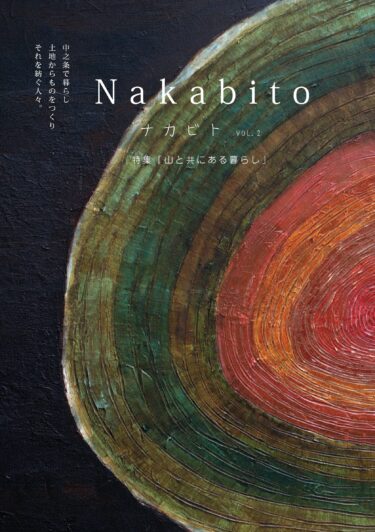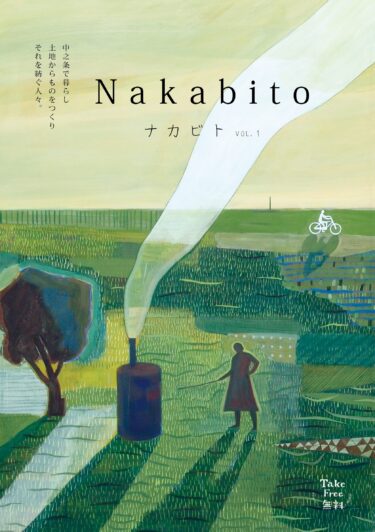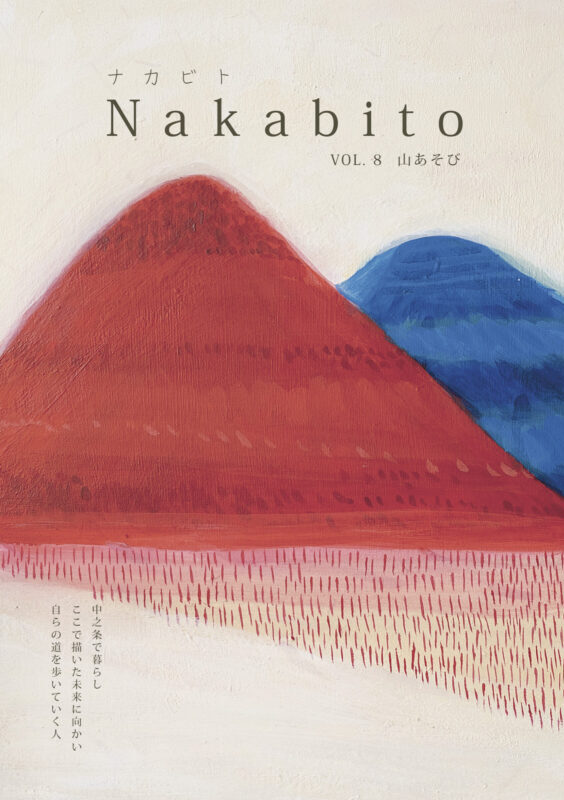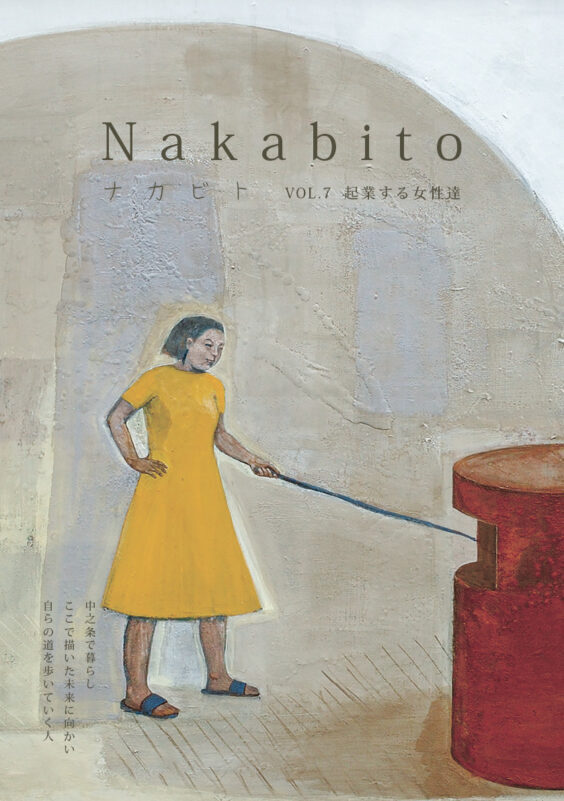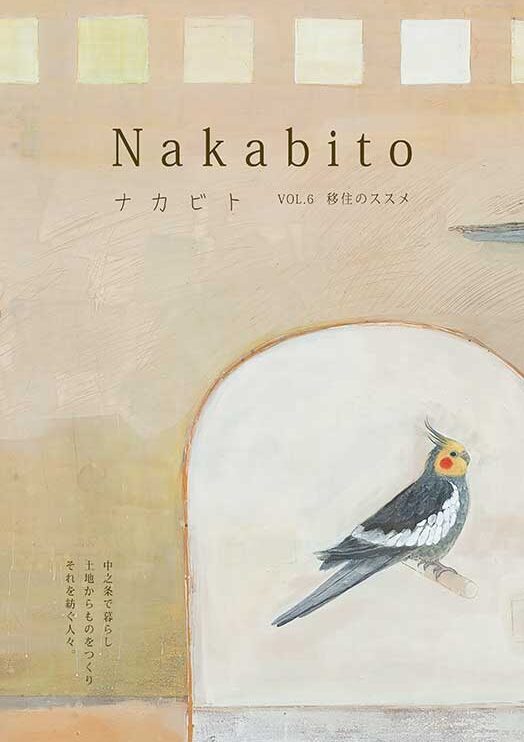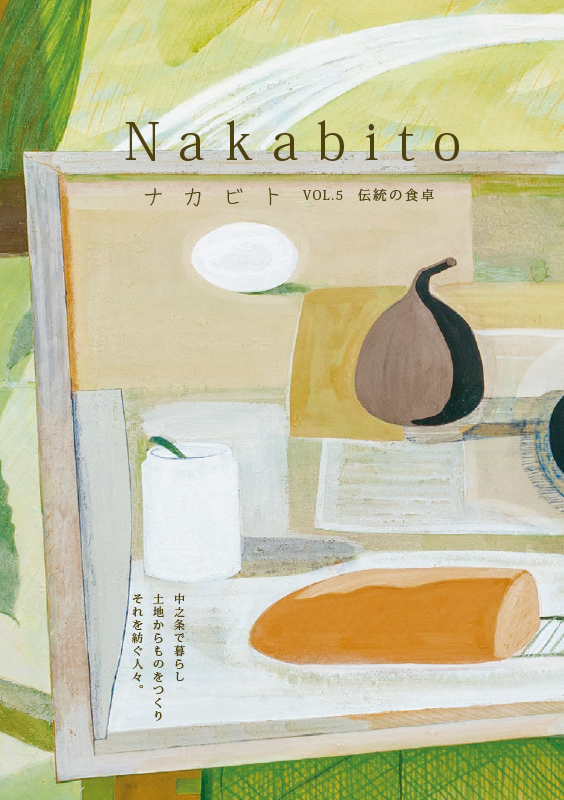糸井さんは、写真家で、木こりだ。
約一年前に、糸井さんが中之条で木こりになるらしい、と知ったときにはとても驚いたし、正直なところ半信半疑にも思っていた。けれど彼はこうして本当に、木こりとなった。
チェーンソーの音が独特なリズムと抑揚であちこちから響きわたる林業の現場は、独特だ。草を踏む音。朝の山の冴えた空気。
「まずはこの木から伐ります」「そちらに倒すので気を付けて」
「次にこの木」「枝が絡まっているので、こっちの木から伐ります」「次はここ」・・・
糸井さんの動きは速く、見事な仕事ぶりだ。伐採は複雑に絡み合う枝やツルの具合をみながら進むが、どれも一瞬の判断である。木々は吸い込まれるように同じ場所、同じ向きに倒れ込んでいく。目の前の景色がみるみる変わる。こちらがあっけにとられていると、糸井さんは「速くしないと怒られるから」と笑った。
森では五感が研ぎ澄まされる、勘が冴える、と糸井さんは言う。「木こりは楽しいです。気持ちがいい」とすがすがしい。
森は、木こりになる以前から、糸井さんにとって重要な意味を持つ場所だ。
糸井さんは、作品を通して様々な事象を森に投影する。そのひとつが、〝境界〟だ。
アメリカの大学に学び、その後の人生の三分の一を、撮影のために海外で過ごしてきた糸井さんは、いつしか、国籍、国境、内と外など、〝境界〟を強く意識するようになったという。そしてそれは、糸井さんの制作に一貫する、根と幹となった。
糸井さんの作品に森が登場するのは10年ほど前からだ。撮影のために訪れたフィンランドで、森に長く滞在する機会があった。北欧特有の深い森で、昼とも夜ともつかないその暗がりに、幾筋も光の線が差し込んでいる光景を目にした。「その光の線は、この世とあの世、こちら側とあちら側といった、境目を象徴するもののように見えた」と言う糸井さんは、その後もフィンランドを訪れ、光と闇が混在する森を写真に撮り続けた。
もうひとつ、糸井さんがフィンランドの森で出会ったのものがある。それは、人と森との関わり方だ。
「ある日、たまたま全伐区という、区画すべての木が切り倒されている、林業の伐採現場に行き当たったんです。それは衝撃的な場面だったんですが、後になって森を維持していくのに必要なことだと知りました。成長しきった木を伐ることで若芽の発育を促し、森の命を循環させる。そうやって人の手で森の環境を守り、そこにフィンランドの人たちは別荘を建てて、週末、楽しむために過ごすんです」
それらの体験は、ひとつの作品シリーズとなり、その完成から5年後、糸井さんは中之条で木こりになった。
いずれは自伐型林業がしたい、と糸井さんは言う。自伐型とは、個人や世帯といった小規模な体制で山や森林を管理する、新しい林業の形態だ。
「写真は100年先まで、自分の命が尽きた後までも存在できるもの。自分の生きた証が、写真という形で残ります。樹木の生長も100年単位。林業は100年先を見るような長い視野が必要で、写真と重なり合う部分があります。いま、日本の林業は衰退し、山が荒れてきている現状がありますが、一人の力では限界があるというのが実情。それでも、自分なりの方法を模索し、続けていきたいと思っています」
糸井さんが見つめる、森と、林業の、光と陰。いつか糸井さんが自分だけの森を持つとき、その森はどんな光景を見せてくれるのだろうか。
この世界、宇宙のすべてを意味する〝森羅万象〟という言葉には、〝森〟の一字が入っている。生も死もすっぽり覆いこみ、生き物が互いに絡み合うようにして形づくる森は、まるでひとつの大きな生命のようだ。
生と死の貯蔵庫のような森。ふと、世界の中心がもしあるなら、それは森なのかもしれないと思う。それでいて、世界の際(きわ)に存在している。一番近くて、最も遠い場所。依然として深く大きく、捉えどころがない、神聖で犯しがたい森。糸井さんは写真家として、木こりとして、その中に立ち続けている。