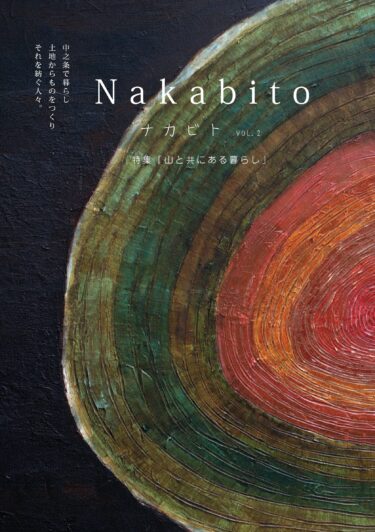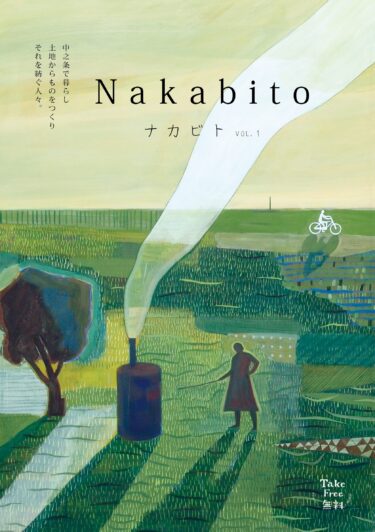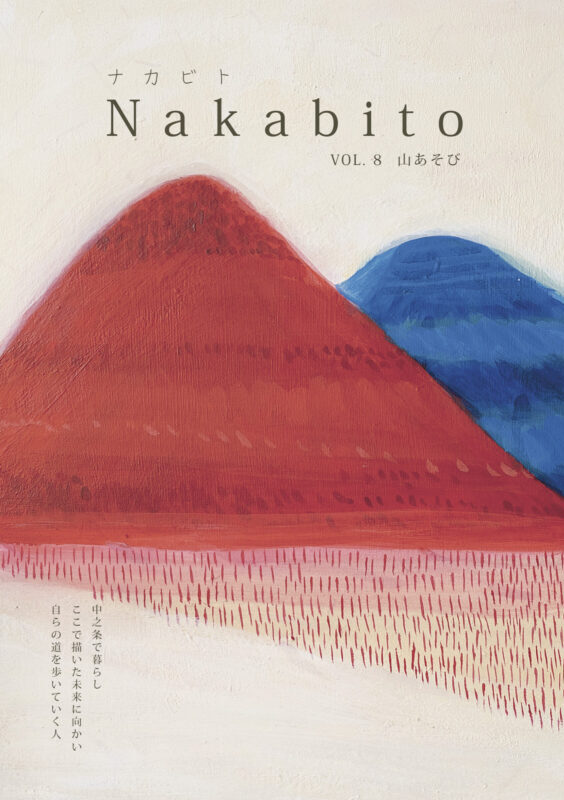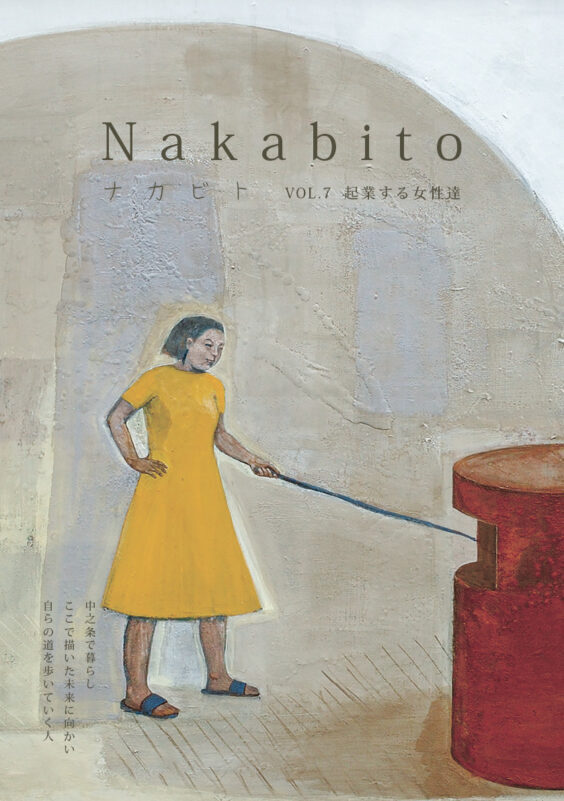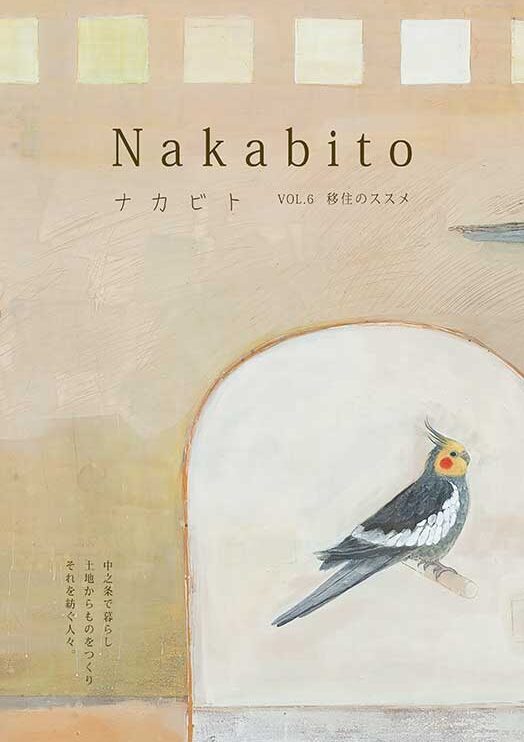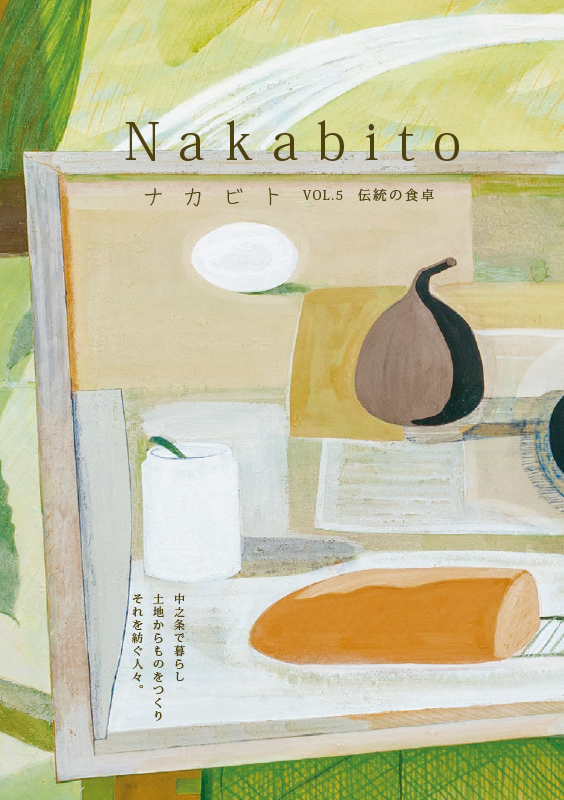クミン、シナモン、コリアンダー、グリーンカルダモン、八角、グローブ。それらスパイスの原型を木製のスパイスミルでごりごりと潰していく。手に伝わるのは、固さや繊維感。香り立つのは、爽やかさ、甘さ、鼻の奥をつくような刺激。「人は本来、体の不調を自分で感知して治すための行動がとれます。スパイスは香りだけじゃなくてそれぞれに消化促進や抗酸化作用などの効能があり、自分が好きな香りは実は、今体に必要なものなんです。だからこれから作るスパイスミックスは、人ぞれぞれで配分が変わる」そう語る古平賢志さんは、顎髭を長く伸ばし仙人のような風貌。奥さんの夏恵さんが明るくテキパキとこのスパイス教室をサポートする。やがて賢志さんが作る日本人の好みに寄せないカレーが運ばれてきて、各々は自分が調合したスパイスを足しながらその滋味を味わう。会場となった六合・赤岩地区の山里ならではの空気も相まって、ゆったりとした、贅沢な時間が流れていた。
賢志さんは、料理教室の先生というわけではない。千葉県松戸市にも小さな飲食店を持ち、中之条町近辺の店を借りてカレーを提供することもあれば、中之条ガーデンズや妙義のゲストハウスで食を介したイベントを行うこともある。自身で職業を言い表すなら「媒介者ですかね」とぽつり。
前橋市に生まれ、渋川市の高校へ通った。父親は仕事の傍ら、30数年前から東吾妻町の山奥に自らで山小屋を建てていた。そこへ行ったりキャンプをしたり、山への愛着は昔からあった。18歳で上京し、その後アーティストや不動産屋などがまちづくりを活性化させている松戸市へ。モテそうだから、という軽い理由で食のサービスマンを始めた。フレンチの店でワインのソムリエをしたり、クラフトビールの店で提供や説明役を担ったり。カフェの店長も務めたし、新規開店するカフェへのアドバイスなど、飲食コンサルタントの仕事もした。けれどある時から料理そのものや提供よりも、酒や料理の背景にある文化や生産者の営み、宗教性や歴史に興味を持つようになる。普段お客さんに提供されるもの、お客さんが欲するものは食の表面的な部分のみであり、もっと深いものを知りたい伝えたいと思うようになった。
千葉県出身の夏恵さんとも松戸で知り合い結婚した。夏恵さんの賢志さんに対する最初の印象は「作る飯がやたらに美味い人」だったと言う。その頃の賢志さんは、様々な飲食店に関係しながら独学で料理を学んでいた。
賢志さんがスパイスに目覚めたのは30歳の頃。来日していたネパール人の友人に誘われて彼の祖国へ。ファーストフードの対極にあるような、そこにある食材で、そこでできる調理方法で作られる料理たち。常用されるスパイスはその土地で生活するために必要な効用を含んでいる。食と生きることとの距離が近いことに感動した。
3年前にはとうとう、現在も続けている店を松戸に持った。けれどすぐにコロナ禍となり、感染が広まる直前に、前々から誘われていたインドへ旅に出た。インドでは、日本での滞在経験がある人から「日本人はとてもお金持ちなのに、なんで悲しそうなの?」と尋ねられた。賢志さんが出した答えは、無駄だ無駄だとそぎ落とした中に重要な要素があるのでは、というもの。帰国後は、普通の飲食店は行わないことを積極的に行った。その一つ「MOKUJIKI-黙食-」
は、曹洞宗の黙食に習い、2時間以上をかけて1品1品を黙って手で食べる食事会。生産者、料理人、参加者、やがて自分の命となる食材に感謝しながら手や舌で味わう。そのような活動の延長として2人の足が向いたのが、より命を感じられる群馬の山だった。
群馬へ帰ってきた時に、空気が美味しい、水が美味しいと思った。賢志さんの父が建てたログハウスのそばの湧水を飲んだら、夏恵さんは都会の水道水に拒否反応が出るようになった。夏恵さんは「結婚した時から、私たちはいずれ山で生活するんだな、となんとなく思っていました。賢志さんは土の上に行った方が良い人だなと思っていたし、そういう生活に自分も憧れていました」と語る。
ログハウスは定住には適さず、吾妻で家を探している時に、「道の駅六合」に売られていた地の野菜や豆の豊富さに興味をもった。多くの人が向かう草津温泉の途中を曲がり、奥まったところへ潜っていく土地の印象も良かった。現在2人は赤岩地区に平屋を借り、町内外での様々な活動をスタートさせている。
赤岩への移住者は珍しい。夏野菜をくれるご近所さんに自分も畑をやりたいと伝えたら、ちょうど草刈りに困っていた畑があると快く貸してくれた。地区の掃除やどんど焼きの準備などにも顔を出し、料理用の器を作りたいと賢志さんが言ったら、うちの家の木を切って使って良いという人も出てきた。現在は、六合の食材や経験を松戸に持ち帰り、その豊かさを伝える活動も行っている。
「この土地には自然の中で人が生きるための文化や知恵が残っている。郷土料理や地域文化も学んで、表面的なエンターテイメントではない物語を立ち上げたい」そう語る2人の物語は、まだ始まったばかりだ。