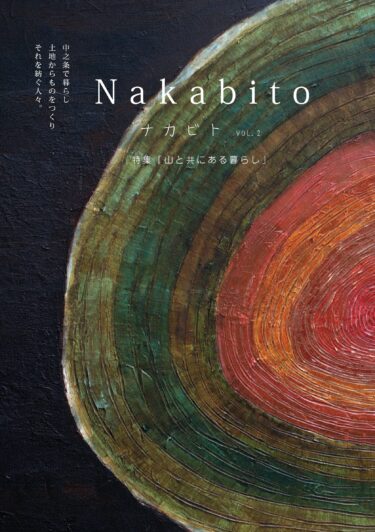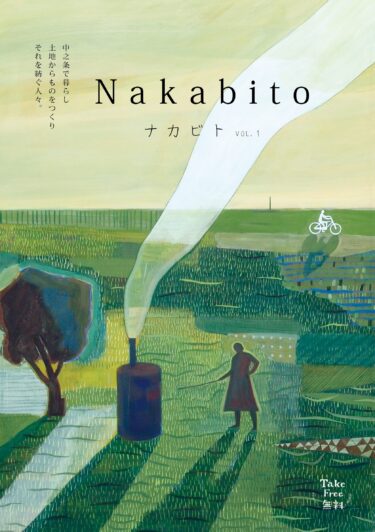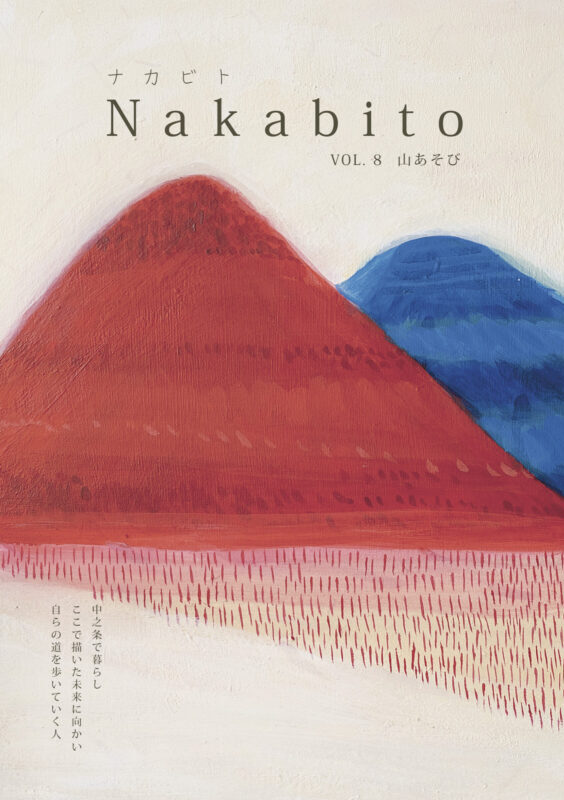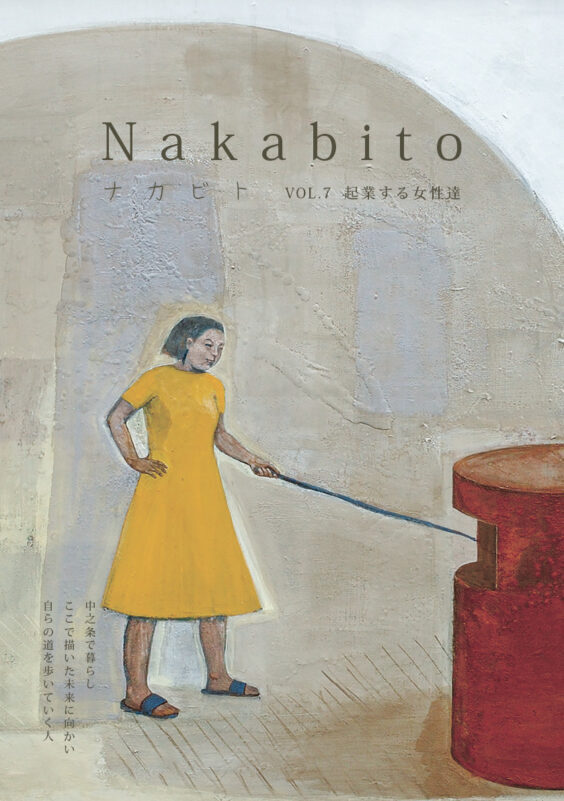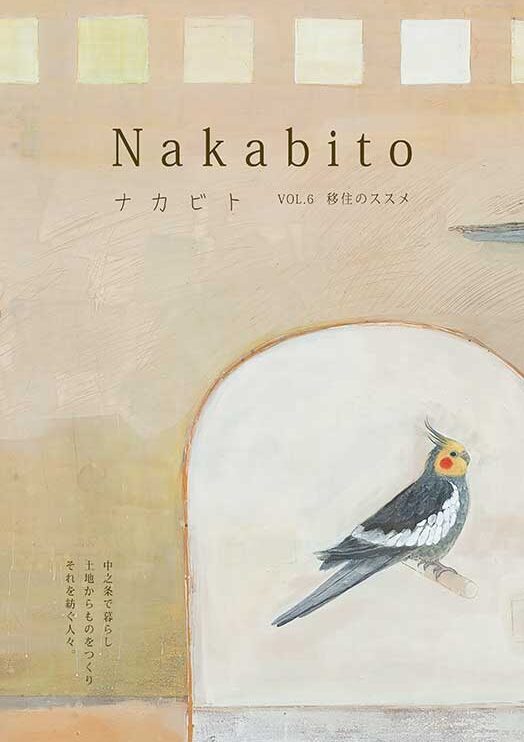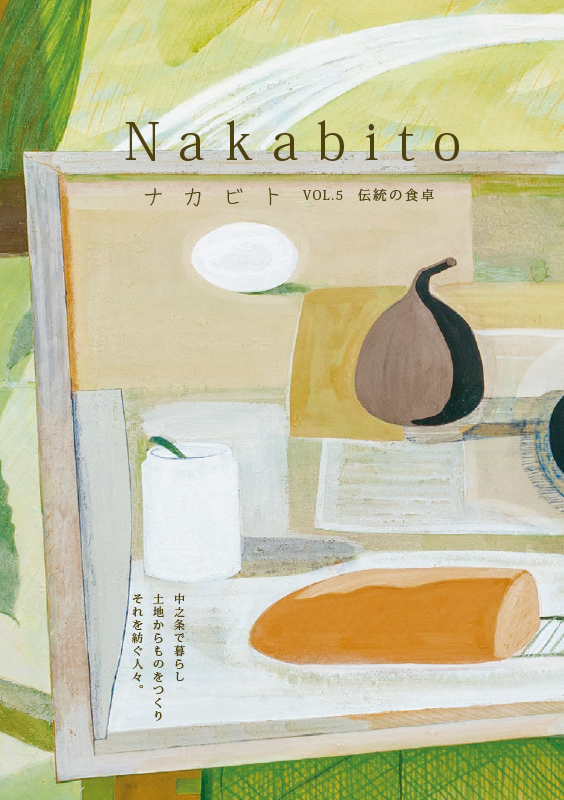植物の種は、地に根を張り、芽吹く。すぐ側でこぼれた種から芽吹くものもあるが、中には風に乗り遠く山を越えた場所に根を下ろす種もある。それは植物に限った話ではなく、人もそう。生まれた場所を離れ「移住」という決断をした人たちは、どんな思いでその地に根を張ろうとしているのだろうか。ここ、中之条町にもすでに、多くの移住者たちがそれぞれの生活を送っている。
12万平方メートルという広い敷地に、バラや花桃など数百種の植物が四季を通じて彩を見せる「中之条ガーデンズ」。花と湯の町を掲げる中之条町が、日本初の女性樹木医である塚本こなみ氏や、日本のガーデンデザインの第一人者である吉谷桂子氏、バラ育種家として多くの著書を持つ河合伸志氏といった第一線の園芸関係者監修のもと、整備を進めているガーデンだ。
色とりどりの薔薇が池や通路との調和を見せながら咲き誇るローズガーデンや、青紫のアゲラタムがまるで海のように広がるスパイラルガーデンが、多くの人を集める。園の奥には北欧風の赤い屋根の小屋があり、その手前のパレットガーデンに、スコップを片手にテキパキと作業をする森山夫婦の姿があった。そのそばでは初夏から秋まで長く咲き続けるエキナセアが赤に黄色に色濃く咲き、白い小さな花束のようなアンミや、まあるい綿帽子のようなアリウムがゆらゆらと風に揺れていた。派手さはないが、立つと心が落ち着く庭。
「北九州市の都市部で育ち、夏休みに玄界灘そばの田舎のおばあちゃんの家に行くのが好きでした。田舎の風景が忘れられなくて。人が苦手だったこともあるけど、幼心に木としゃべりたいと思っていたんですよね。そんなこと、昔は言えなかったんですけど」と話す加南子さんにとって、現在のガーデナー(造園の造作・維持・管理などを行う職)になる道は必然だった。熊本の大学では「環境共生学」を専攻。先にのべた塚本こなみ氏が園長をつとめる「足利フラワーパーク」に研修として入り、就職。のちに吉谷桂子氏がプロデュースしていた「浜松フラワーパーク」でも働いた。浜松では吉谷氏とともに5~6年かけて庭を作り「人工的な造園ではなく、美しい自然や景色を庭に反映させる」吉谷氏の仕事に惹かれていった。2020年4月からは、吉谷氏が関わりガーデナー不在だった中之条ガーデンズで働くこととなり、夫の剛志さんと共に中之条町に移住した。
一方の剛志さんは元から植物や園芸に関心があったわけではない。足利の実家が土木工事の仕事をしていて大学も建築を専攻。親の仕事を手伝い、それに嫌気がさして足利フラワーパークに就職した。そこで加南子さんと出会い、二人は後に浜松、中之条と暮らしを共にするようになる。現在は加南子さんと同じガーデナーとなり、花に囲まれる毎日。植物や園芸の話になると目を輝かせて前のめりになる加南子さんとは対照的に、剛志さんはその隣で静かに、にこにこと彼女の話を聞いていた。「彼はいつもフラットで、私のイメージや理想を緩めてくれている。助かっています」とは加南子さんの話で、なるほどこの2人だからこそ、高い目標を持ちながらも着実に、理想の庭への歩みを進められるのだろう。
中之条ガーデンズは2021年春、グランドオープンを迎える。足利、浜松と2つの庭園で働いた経験があっても、今現在は作業に追われ、仕事を楽しむ余裕もない状況。役場職員やパート、ボランティアと共に多忙な業務をこなしている。そんな忙しい中であっても、2人が見る先は明るい。
「パレットガーデンの花はバラのような強い存在感はないけれど、この庭は命としての美しさを伝えられる庭にしていきたい。枯れたものとか、それが種になってまた花になっていくこととか。この小屋ではそんな循環を見せるワークショップや、見るだけじゃない植物の魅力、ハーブの使い方なども伝えていきたい」と加南子さん。中之条ガーデンズが、他県から来た人がまずここに来て「中之条町っていいところだな」と思えるアイコンになれば良い。それには、外から来た私たちだからこそできることもあるのかなと思っています、と話を続けた。
この町に暮らしはじめ、種を植え続ける2人の姿を見て、観光地としての華々しい庭園だけではない、心安らげる庭園の未来像が見えた気がした。