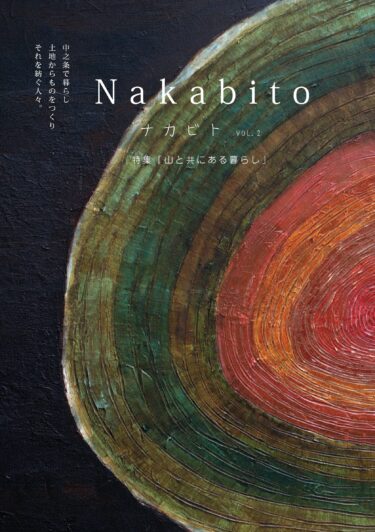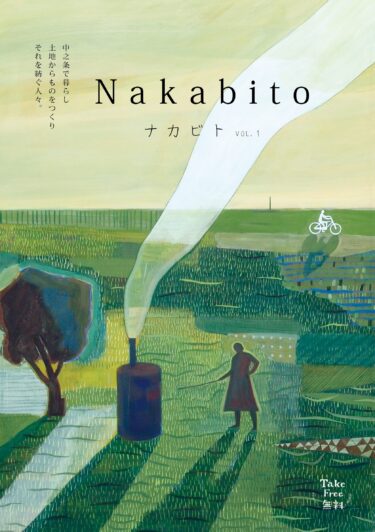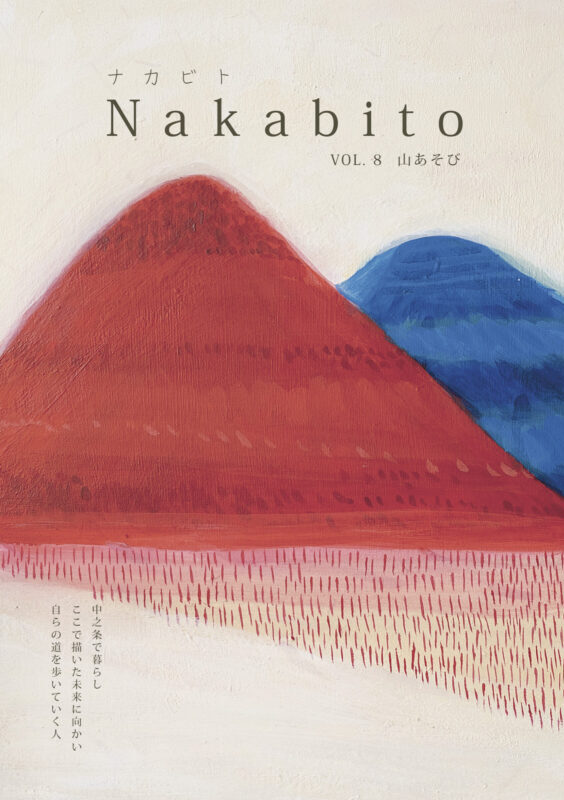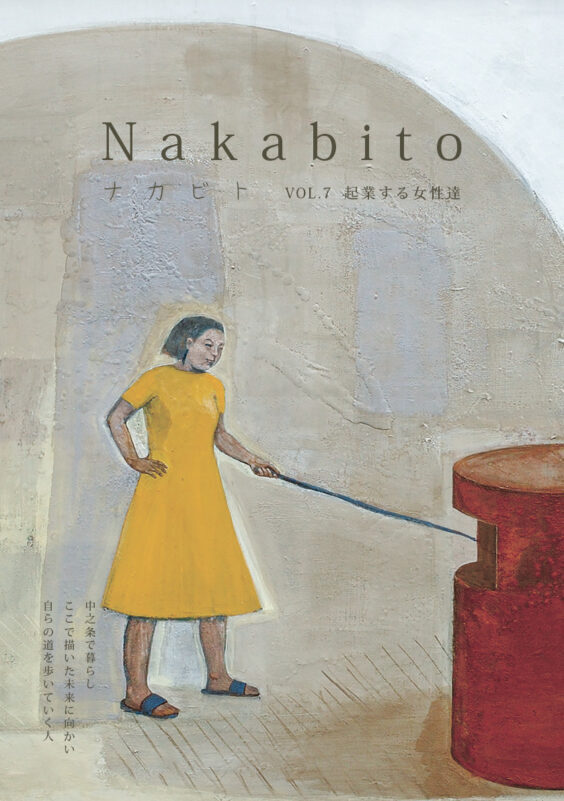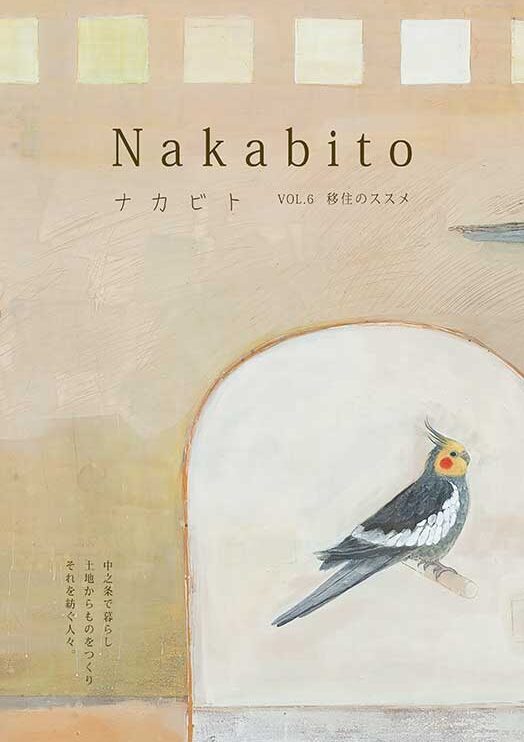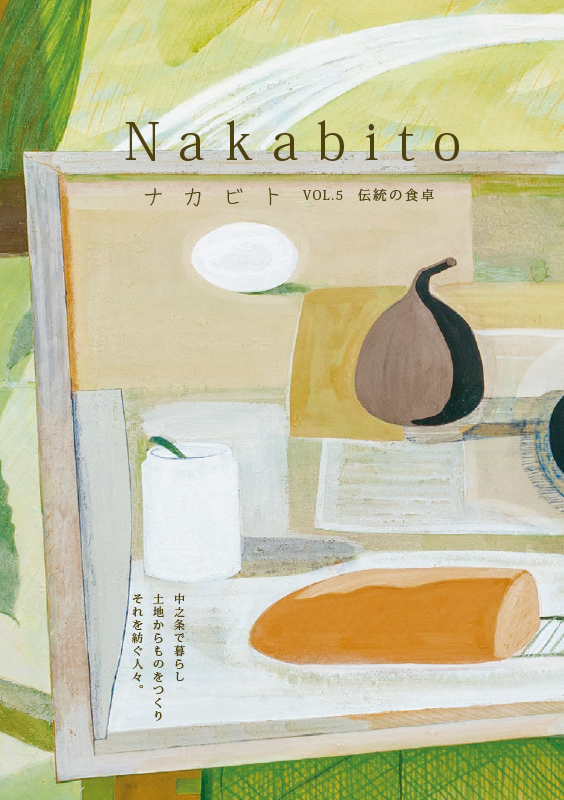大小の石がゴロゴロと取り囲む、齋木さんの作業場。巨大な回転式の刃がついた石切りの機械が異様な存在感で鎮座し、ノミや金づちなどのさまざまな石工道具たちは、みな一様に、灰色の砂にまみれている。
その荒涼ともいえる景色の片隅に、穏やかな表情の観音像が横たわっていた。まだまどろみの中のように、穏やかな表情を浮かべている。周囲の重々しい石と同じもののはずなのに、まったく別の何かに見えた。石という硬く分厚い殻を破り、たった今生まれ出たばかりのような柔らかそうな頬。その丸みに、齋木さんは、そっと、ノミをあてた。
コツコツコツコツ…
静寂に響く音は、石と石工だけが交わすことのできる言葉みたいだ。地面には石から削りとられた後の、細かくキレイな砂が一面に敷き積もっている。
齋木さんの顔に汗がながれ、像にしみを作った。石と人が向き合う時間が、厳かに流れていた。
「地味でしょ」ひととおりの作業を終えると、齊木さんは、ひとこと言って笑った。
いつもの齋木さんの笑顔。ふと、張りつめていた空気が緩んだ。
齋木さんの石工の仕事を見せてもらうのは、この日が初めてだった。
日ごろから知る齋木さんは本当に多彩な人で、小気味よくブルースギターを爪弾けば、その美声とともにステージに立つこともある。そして、石工であり、石彫作家。
中之条で生まれ育ち、石材店『齋木七郎石材本家』は父である七郎さんから引き継いだ。現在は齋木さんのお兄さんとその息子の3人で切り盛りをしている。
「親の背中を見て育ってきましたから。漠然と、自分もそうなるんだろうなと思っていましたね」
子どもの頃から当たり前のように石の仕事があり、学校から帰れば、家ではみんなが仕事をする姿がいつもあった。
でも、齊木さんはただの石工の道を選ばずに、高校卒業後すぐに彫刻家のもとへ修行に出て、石彫作家となった。
現在は、国内外の個展やさまざまな展覧会で作品を発表している。町を舞台にした二年に一度の国際芸術祭『中之条ビエンナーレ』へも出品を重ねる。職人、アーティストという二面性には、「作っている本人がひとりというだけ」と、仕事であろうと制作であろうと、なにも変わるところはない。そんな自然体な姿勢は、とても齋木さんらしいなと思う。
齋木さんが手がけた仕事で語らぬわけにはいかない、2015年の霊山嵩山三十三観音の修復がある。嵩山は古くから町の人の信仰を集めてきた重要な山だ。その山の33か所に祀られている観音像を一体一体背負って山を下り、修復し、生まれ変わったものを背負い、ふたたび山を登る…という大仕事を、二年がかりでやり遂げた。300年の時を経た観音像を、またその先の未来へとつなぐ。齋木さんは石工の仕事を、〝地味〟なんて言うけれど、とんでもない。なんてすごいスケールなんだろう。
「石という素材は、良くも悪くも自分の仕事が長く後世に残ってしまう。それはひとりの物づくりの人間からすると、ふと我に返ったとき恐ろしくなります。石は何万年何億年とある存在。たとえば石を割ったら、内部はそのとき初めて空気に触れるわけです。彫らせてもらう、という気持ちでやっています」
妥協を許さない石工の仕事。石と対峙する厳しさ。けれど、ときおり、何百年前の石の修復の際に昔の職人さんの〝粋な計らい〟、〝遊び心〟を見つけることがあり、「そんなとき、ほっとする」と、柔和な表情を見せた。石の中に眠る長い年月のなかで、時を超えて別の時代の職人同士が出会い、技が交錯している。石工の仕事は、終わりのないバトンリレーのようだ。
齋木さんは謙虚に「これが仕事だから。これしかできない」と言う。でも、石工が入れるノミの一刀目から、石はただの石ではなくなり、その瞬間から人と石の物語が始まる。
「生まれた場所でものをつくることは楽しい」と、誇りと喜びを語る齋木さんは、生まれ故郷であるこの町で、これからも、新たに100年200年先に続く石の作品を、〝コツコツ〟と刻み続けていく。長い年月、土や砂が重なり、重なり合って、ひとつの石になるように。