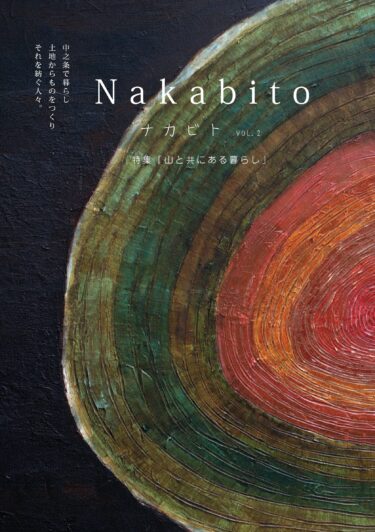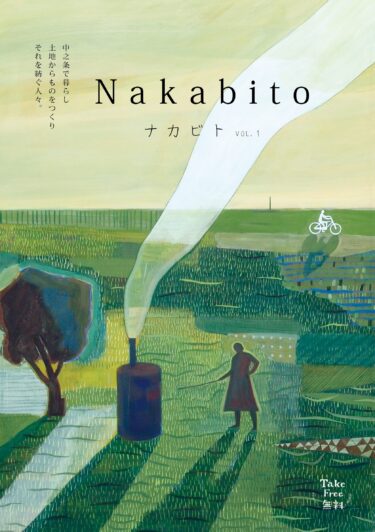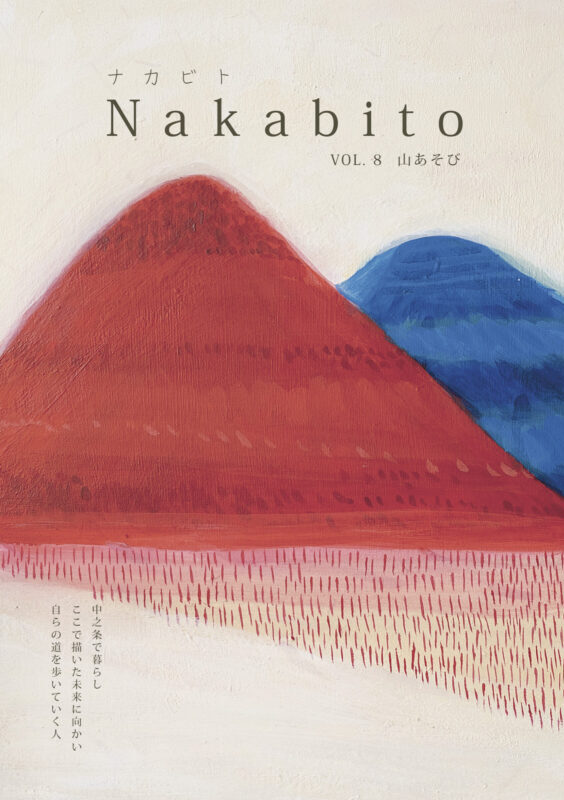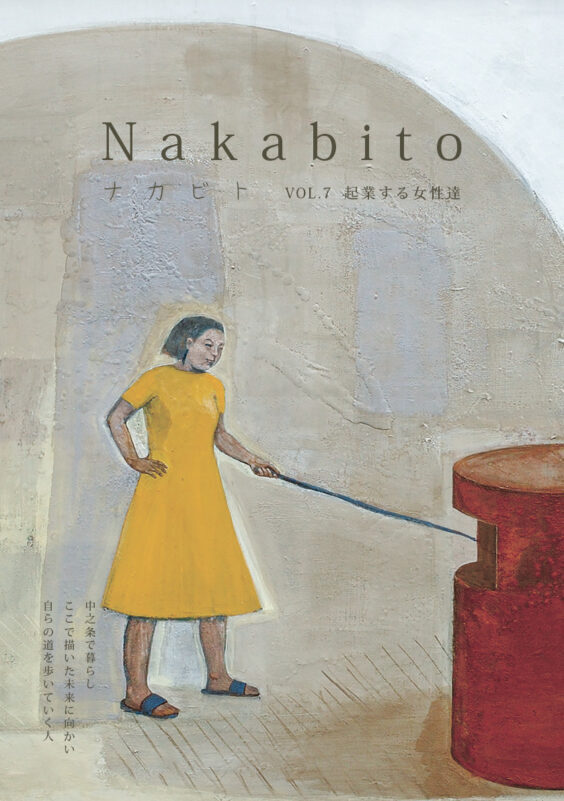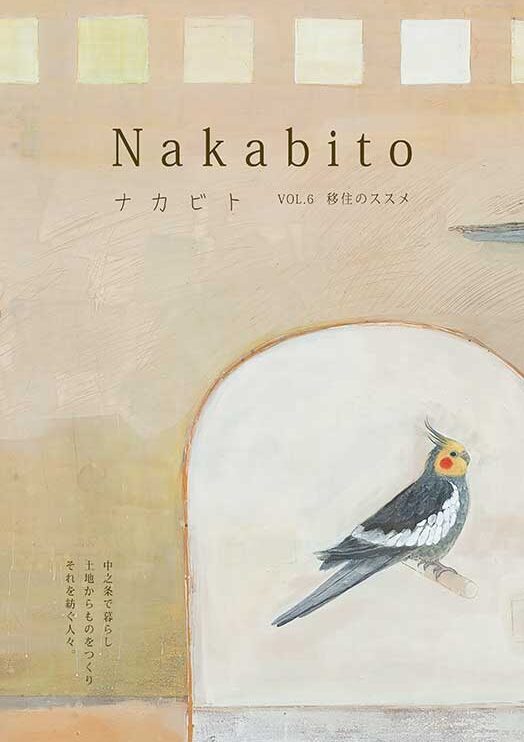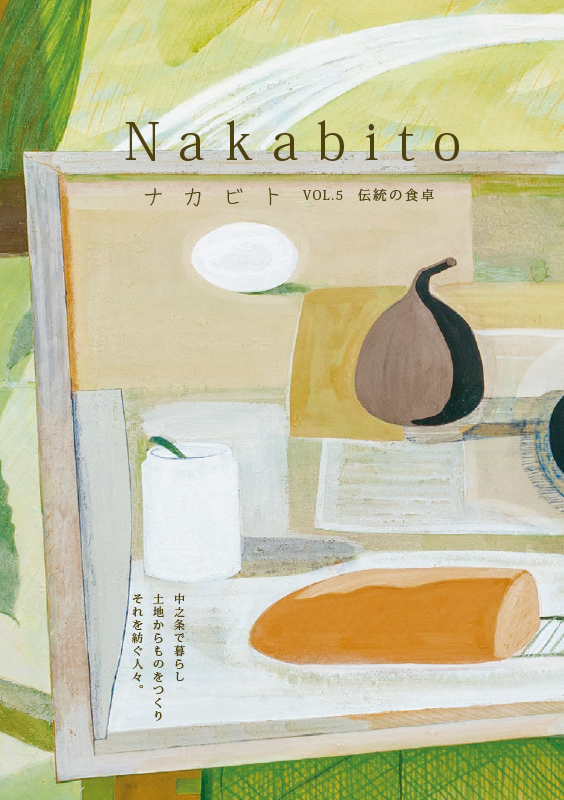ザクザクと、膝まで積もった雪を踏みしめながら、関千代衛さんの後にわたしたちは続いた。そうして、ある1本の木にたどりついた。立派なトチの木。真っ白な大地にすっくと伸びる幹、葉を落とした枝先を堂々と空へ広げ、立っていた。
この木はいまから伐り倒されようとしている。物言わず動かず、凛として佇む姿は、自らの運命としずかに向き合っているように見えた。
関さんがチェーンソーのエンジンをかけると、シンと静まる山にけたたましい音が響き渡った。幹に刃が入れられる。木は一寸も動かない。大きな木と対照的に、ひとりの人間のなんと小さいことか。いくつもあるチェーンソーや斧を駆使し、倒れる方向を計算して切り込みを作っていく。関さんは冷静で、その動作ひとつひとつ、初めからすべてが分かっているかのように確信がみえる。刃の長さが1メートル以上もある大きなチェーンソーにも翻弄されることはない。道具は関さんの身体の一部になっている。
そうして最後の一刀を加えると、あんなにも動じなかった木がすさまじい軋み声をあげて傾き始めた。どうとも形容しがたい音。倒れゆく様は、まるでスローモーションのようにゆっくりと。すこしの間、時が止まってしまったかのような、永遠が凝縮した瞬間に感じられた。パキパキッと折れた小枝の破片が雪原に舞い散る。木は、倒れた。
木が伐られるのを見るのも初めてなら、伐られたばかりの木に触れるのも初めてだった。毛羽立った断面は水分をたっぷりと含んでしっとりとしている。そして、ほんのりとあたたかかい。木にはまだ、命が残っていた。
「この木は素直で本当にいい木だ。」
関さんが言った。「トチノキは成長が早くて、素直で潔白で粘り気があって良い木なんだ」。
『木が素直』、とは年輪の成長に偏りがなく、均一できれいな円に成長した木、ということらしい。『粘り気』、は加工の際に割れにくく強い、ということ。このトチノキは関さんの手によってこね鉢になる。木は自らの命を失うが、新たな命を吹き込まれ、暮らしを支えてくれる道具として生まれ変わる。
木を伐り、こね鉢を作る。この最初から最後までの作業を、関さん一人で行う。「今もこんなことを続けてるのはオレだけだ」と笑った。止まらず動き続け、顔には汗が滴っている。86歳だというが、身体に完璧に覚え込ませた動きには一切の迷いもなく、見事という他ない。わたしたちはただ、その光景を固唾をのんで見ているしかなかった。
倒れた木から切り落とした枝を幹の下に敷いて足場にし、根元付近の一番太くて良い部分を、狙った長さに輪切りにする。その際にできる木屑や余った材も無駄なく使う。木の切り口をそれらで塞ぐのだ。切ったばかりの木材は、適切に水分を抜かないとヒビが入ったり割れてしまうという。不用意に乾燥させないための工夫だ。
直径とほぼ同じ長さに輪切りされた丸太を、縦に5等分にし、表皮側を除いた3枚の板が出来上がった。ここから2つのこね鉢と、2枚のまな板ができる。
関さんはとても明朗快活なひとだ。「今日一日がんばれば、三日寝て起きるくらいがちょうどいい」と冗談をいうが、軽妙な語り口は若者になど負けない。生きた言葉が矢のようにつぎつぎ飛び出してくる。よく話す。よく笑う。家事もぜんぶ自分でこなす。「その方が楽だい。食べ物でもなんでも、自分の好きなもんを適当にやるんサ」。
こね鉢とその歴史について、関さんはこう話す。
「生活の中での伝統工芸は、こね鉢が一番古いのではないか・・・」 同時に、「一番早く始まって一番早く衰えていった」と。
「うどん」や「すいとん」などの粉ものが主食だったころは、こね鉢は欠くことのできない重要な道具だった。ところが既製の麺製品がいくらでも手軽に買える現代、その役目を急速に終わらせつつある。こね鉢の伝統を途絶えさせまいと立ち上がったひとりが、関さんだ。いまもなお技術を受け継いでいるのはひとりしかいない。「しょうしい(恥ずかしい)」とはにかみながらも、その表情には長い間に培ってきた自信と誇りがにじむ。
関さんは、山肌に張り付くようにしてある世立(よだて)というところに住んでいる。この地域では大地がもたらす作物の恵はほんのわずか。代わりに生活を支えたのが、狩猟と、周囲に豊富にある木々を利用した木工だった。身の回りの木で生活用品をつくることは日常の仕事であり、暮らしの一部だった。なかでも、こね鉢は必需品であると同時に、売れば一番良い商売になったという。電動工具などない時代、すべてを人の手で作るのは大変な根気と労力が必要。完成した立派なこね鉢を関さんの父が背中に担いで山を下り、帰りには米を背負ってもどってくる、そのとき持ち帰った米の多さを、まだこどもだった関さんはよく覚えていた。
「山には生きられるなにかがある。」
「オレはただの木こり。」
とてもシンプルな言葉だが、鮮明に響く。関さんの暮らしは、いまも山と木とともにある。
こね鉢づくりは、関さんの作業場で。伐られたばかりの木はまだ充分に水分を含んでいて、柔らかく削りやすい。乾かないよう度々水に浸して、湿った状態で作業を進める。削りだす前の工程はとても大事だ。ここでも関さんの経験や知識が大いに発揮される。完成後の中心点を決める作業は後々にまで影響し、慎重さと正確さが必要となる。中心点は底面と上面でぴたりと一致していなくてはならないのだが、このやり方、説明をそばで見聞きしてはいても、なかなかどうして複雑だ。また、削り終わったあとにこね鉢が乾燥する際の、木の「縮み」を考慮する工夫。木目の向きで縮みに差が出るため、すこし楕円形に作る、など。関さんにとってはまるで当たり前に、事もなく行うひとつひとつに、驚きや深い発見がある。
使う金物道具は見慣れたものから見たことのないものまで、種類もサイズもじつにさまざま。名前もない関さんオリジナルの道具もある。幾度となく握られたであろう角がとれたピカピカな木の握り部分は、何十年にもわたる関さんの膨大な仕事量をありありと物語っている。
作り置きはせず注文にのみ応じている関さんに大量生産についてどう思うか聞くと、「まったく興味がない」と。
「使う人の顔がこね鉢に見える。自分のぜんぶをまるっきり込めて作っている。」
誰が使うかわからないもの作りはしたくない、と話しながら手を動かすその仕事には、温かな血がたしかに通っていた。