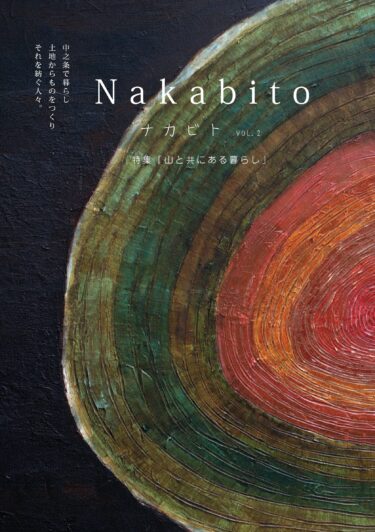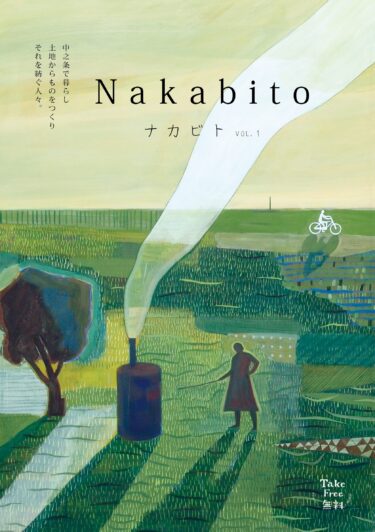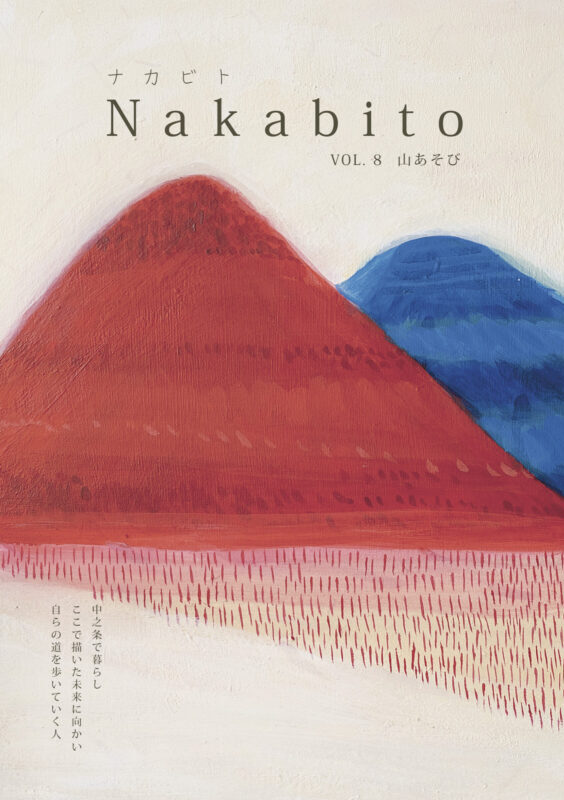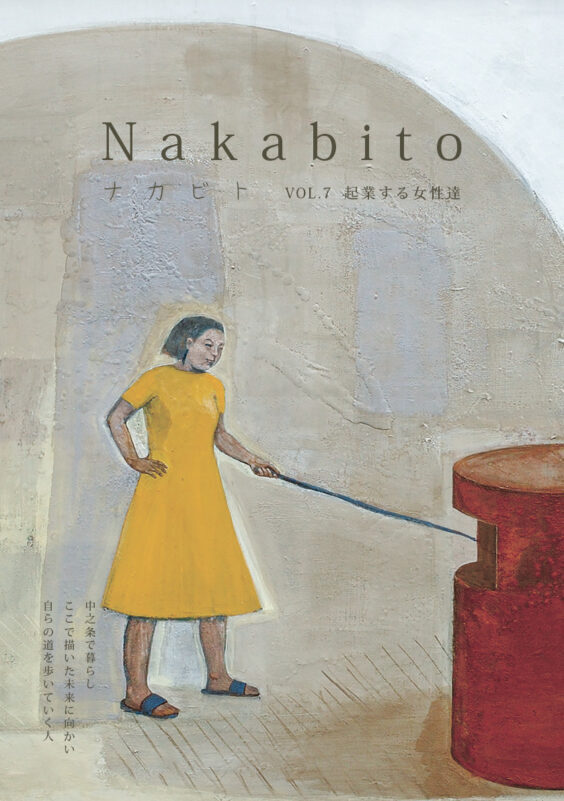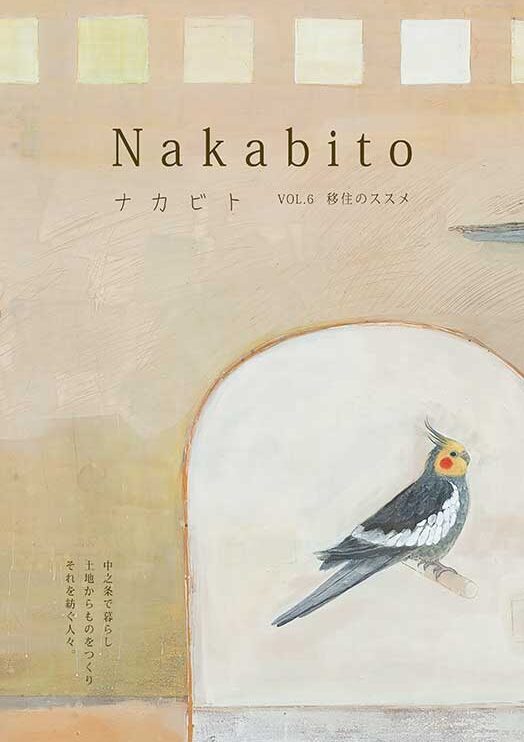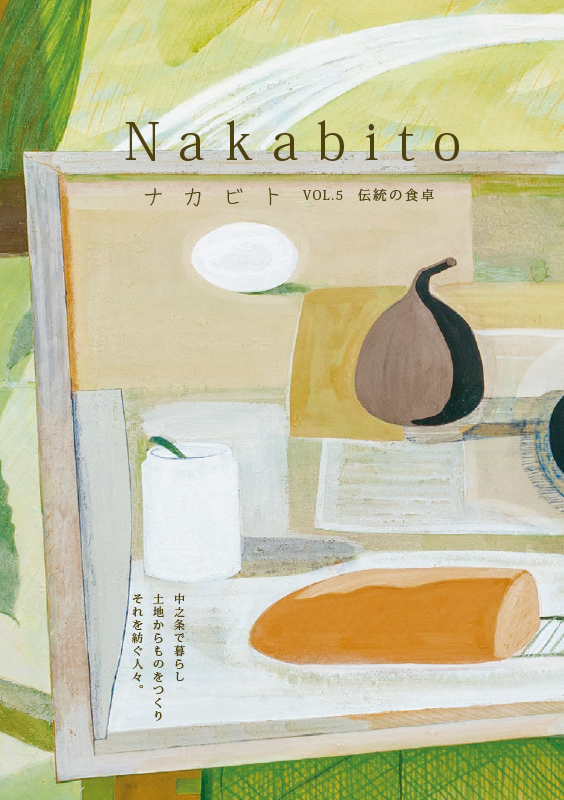話は再び芳ヶ平湿原に戻る。おむすびも転げ落ちる急斜面であることから「おむすび山」という通称が付いた小高い山をスノーシューで登る。このあたりになると標高は1800メートル。振り返れば草津温泉の街並みが遠くに低く見え、普段の生活圏ではなく何か別世界にいるような、自然の真っただ中にいるという事を、肌感覚で感じる。ガイドの木村さん先導のもと、山頂の木々の間を抜け、なだらかな斜面を降りていくと、その緩やかな傾斜の行きつく先に小さな赤い屋根が見えた。目的地となる芳ヶ平ヒュッテだ。大自然の中にぽつんと存在する人の営みが、これほど嬉しいものだとは思わなかった。
ヒュッテに着くや否や、毛むくじゃらな大きな犬に取り囲まれた。ここで飼われているビアデッド・コリーのセレン、クッカ、トゥーリだ。少し遅れて、ここを営む新堀研二さんと弘子さん夫婦が出迎えてくれた。雪を払って小屋に入ると、薪ストーブが焚かれ、軽快なジャズが流れている。木張りの壁にはクラシックなスキーや、ここで飼われてきた歴代のコリーたちが描かれた絵画が飾られている。質素な山小屋というイメージとは違い、けれど派手ではない。あるもの全てがここに馴染んでいる。
芳ヶ平ヒュッテの歴史は長い。芳ヶ平には戦前から、大学生がスキーをする際に泊まるための小屋があった。芳ヶ平ヒュッテという名で県が最初に山小屋を建てたのは戦後の1951年。スキー客をもてなすだけではなく、遭難などのトラブルを防ぐ役目も果たしていた。1972年には現在の場所に作り直され、初代管理人の息子が後を継いだが、1993年頃からは管理人不在となり、閉じられることとなった。
研二さんの人生は破天荒だ。東京は世田谷に生まれ、スキーと共に人生を過ごしてきた。23歳の時、アメリカ横断を経験した先輩から「スノーモービルでカナダを横断しないか?」と声をかけられた。仕事を辞めて、トロントからバンクーバーまで二か月半の旅。当時は、スキーバムと呼ばれる定まった職を持たずに季節ごとに国を変えてスキーをする人たちがいて、その中に混じり一緒に滑ったこともある。その後はバンクーバーで4年ほどヒッピーのような暮らしをした。落ち着いた山小屋のオーナーという今の雰囲気からは想像できない過去だ。
29歳で帰国し東京で服屋になる。15年間その仕事に就きながら、その間に弘子さんとも出会った。その後、40代なかばに洋服屋の仕事を辞めた。横手山にスキーに行ったことをきっかけに横手山頂ヒュッテで働くことになった。その社長から「芳ヶ平ヒュッテが空いているから、管理人をやらないか?」と言われ「やりたいです」と即答した。自分の山小屋を持つこと・・それこそまさに、研二さんの昔からの夢だったのだ。
研二さん夫婦は、1998年にはじめて芳ヶ平ヒュッテを訪れた。壁はベニヤでほこりが層を成していた。県による工事が始まるまで1年くらいかかったが、改修工事は想像以上の大工事で、壁は全て張り替えられ、水洗トイレやシャワーや厨房も新しく作られた。汚水を一切外に流さない浄化槽は当時最先端の技術。営業を行いながら、夫婦が愛着を持つ家具や食器を増やしていった。
営業は順調だったわけではない。開店直後の冬の泊まり予約は一切なく来客すらない。春になればと思ったが6月になってもお客さんは全然来ない。その頃、小屋が再開したことをNHKで取り上げられ、7月8月の週末が予約で埋まった。喜んだのも束の間、「芳ヶ平の上の道までは来たんですけど、霧が深いので止めておきます」などキャンセルが多発。予約金を取るようになってからはようやく安定し始めた。15年ほど前には草津白根山の警戒度が2に上がり一部道路が閉鎖。日帰り客が8割減ったこともあったが、今まで続けられたのはリピーターの存在が大きい。常連さんは、ここに泊まった翌朝、1年後の予約を入れて帰っていくという。
夜が近づく頃、研二さんが室内のランプに火を灯し始めた。山での暮らしで必須となる節電のために始めたランプだったが、電気を消しての火の灯りは何よりの演出となった。食事の支度は弘子さんの仕事。テーブルに並んだのは、にんにくスープ、ニンジンとカッテージチーズのサラダ、煮物、そして国産牛の手作りハンバーグ。食材の運び込みに非常に労する場所にありながら、レトルト食品などは一切使わない。雪山を一歩一歩踏みしめここまで来た今日の旅を振り返り、美味しい食事をゆっくり進めると、今日に至るまでの日々までも肯定されたかのような幸福感に包まれた。
最後、研二さんに長年ここにいて飽きないですか?という不躾な質問をしてみた。
「飽きないですね。カナダを横断していて思ったのは、360度の雪の大平原は最初こそ感動しても1週間くらいすると山が見たくなる。日本人はここ住めねぇなってことなんですよ。この土地は一方はバーッと開けてるけど、裏は森。来た時もいいなーと思ったし、今も飽きない」
翌早朝、周囲を歩きながら、森の中に沈みゆく満月と、大平原の先で橙色を纏い昇る太陽を見た。芳ヶ平ヒュッテは昔も今も、訪れた人たちの胸の中に、灯台のように灯り続けている。