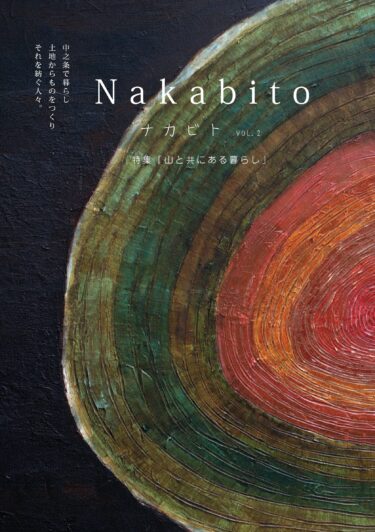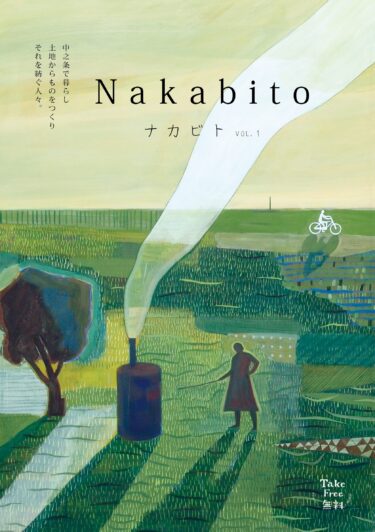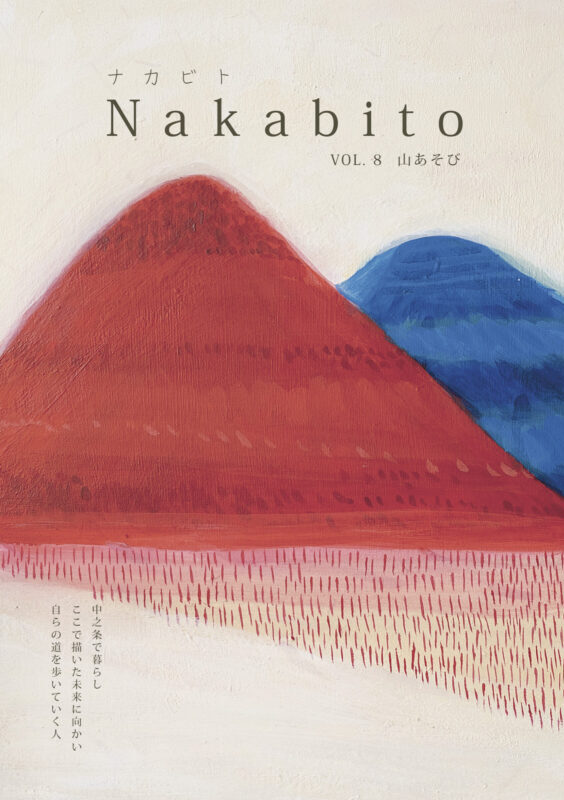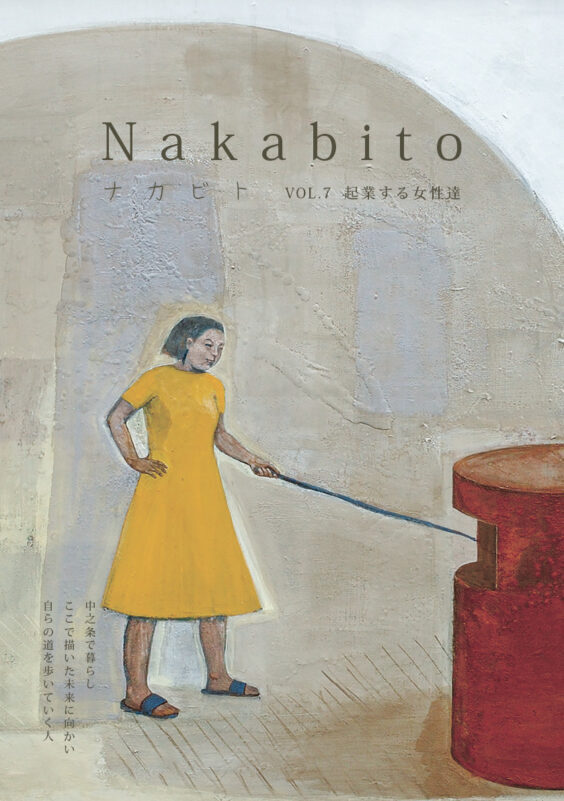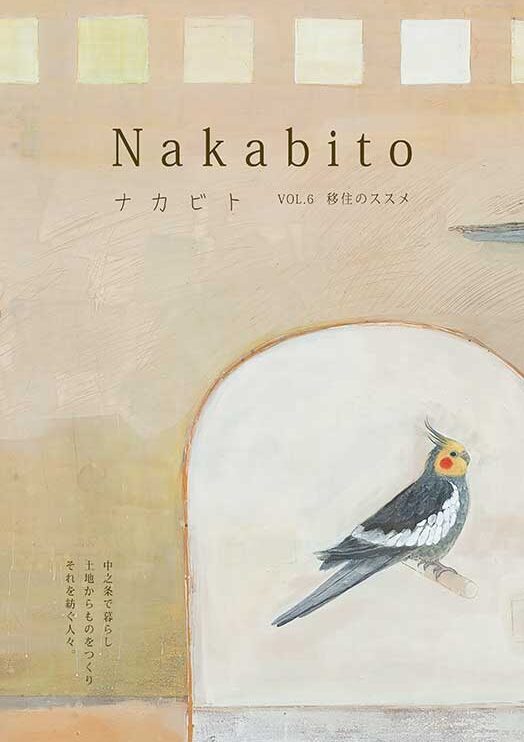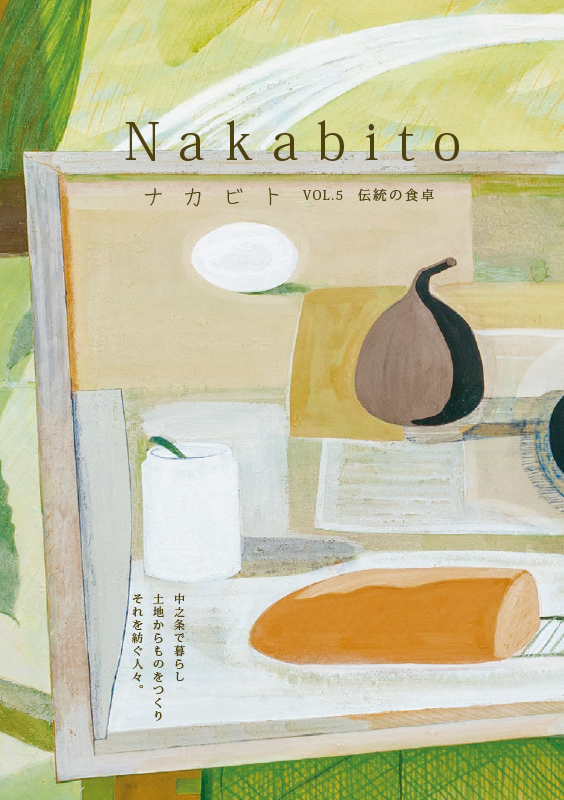六合 。他の集落から離れ、山と森にひっそりと隠れたように存在する、住民わずか10人足らずのちいさな集落に、染織作家 行松啓子さんの自宅兼工房はある。訪れる人も通り過ぎる人もほとんどいないというこの静かな環境を好み、ひとり、布づくりに没頭する日々を送っている。ここでの暮らしについて訊ねると、「普通です。たぶん普通だから暮らしていられるんだと思います」と答える行松さんは、まっすぐで飾るところがない。大阪出身の行松さんにとって、六合の魅力とは。「この場所は『ドン付き』なんです。文化が行きどまって留まり、むかしのまま残っている」と言う。「ねどふみ」やスゲ細工の技法、それを受け継いできた女衆(おんなしょ)たちの暮らし。それらは文化的にとても豊かだ、と。織物を始めたきっかけは、「(『鶴の恩返し』の)鶴になりかった」と笑った。しかし、ひとたび機織りが始まると、その和やかな空気は一変した。それまで部屋の片隅で重々しい体を横たえていた機織り機はとたんに目を覚まし、美しく繊細な布を生み出しはじめる。そして、規則的でとても冷静な機織りの音色を響かせた。
ジャアアァー、タンタンッ! ジャアアァー、タンタンッ! ジャアアァー・・・
胸の芯に響いてきて、どうしてか心揺さぶられる音。それはもしかしたら、心臓の鼓動に、よく似ているからかもしれない。
「じつは機を織る段階では、仕事としては90パーセントくらい終わっているんです」。織物は、機織りのイメージだけが先行し、その前の工程はあまり知られていない。糸を繰る。六合の山の樹々から色をもらって糸を染める。染液に浸し、媒染液(発色、定着の役割をする)に浸し、を繰り返して染めあげていく。織る前の糸に先染めをして模様を出す場合は、完成後を想定して色を配置しなくてはならない。機(はた)に経糸(たていと)を掛ける。経糸の数は、反物であれば1000本以上。それを順番どおりに1本1本掛けていく。気の遠くなるような作業。でも、行松さんはこれらの工程こそが好きなのだという。
かつては養蚕を営む農家は、きれいな繭は出荷し、売れないくず繭を自分たち用にとっておき野良着などの日常着を作っていた、と話してくれた。私の曾祖母も自家製の絹から日用品や晴れ着を織っていたと母から聞いたことがある。そのころまでは、養蚕、絹、織物は特別なものではなく、ひとびとの日常のほんの一部にすぎず、衣・食・住の一環として存在していた。行松さんが理想とする姿も、まさにそのようなものだ。「普段の生活の中で織物ができる環境をずっと求めている」、「むかしの日本人が生活の片手間でできていたことを、なんで(私は)できないのかな。(布に)時間を費やせば費やすほど、自分は無力だと思う」と。結果的には日常のすべてが布づくりになってしまうという行松さん。とはいえ、行松さんの仕事は、これまでの数多くの経験と技術 ―出雲絣、牛首紬、スコットランドのタータン、タイの絣織物など国内外で幅広い織物の研究をしてきた― が結集したものであり、その作品を見れば、膨大な手間と時間がかかるのは誰もが納得するところ。それでも、「まだ結果が出せていない」と、あくまでも自給自足的な、生活の中での織物を想い描き続ける。
織っている途中の布を見せてもらった。山桜で染めた糸の美しい透明感。優しい薄桃の向こうにいろいろな色が透けて見えるよう。機に緻密に張られた経糸には、先染めされた模様がほんのり浮かび上がっていた。淡く儚い色合いは、そのなかに樹のしたたかな生命力を秘めている。「(鶴のようにいつかは)消えてなくなりたい」と笑う行松さん。それは、自然に生きて、自然に帰る、ということなのだろうか。命の営みの中であるがままに織物と向き合う、そんな行松さんの哲学と信念が、布に映し出されていた。